
七五三は、お子さまの成長を祝い、これからの幸せを祈る日本の大切な行事です。
その際に欠かせないのが「絵馬」への願い事。
とはいえ
「どんなふうに書けばいいの?」
「例文が知りたい!」
と迷う方も多いですよね。
本記事では、
七五三で使える絵馬の基礎知識から、
実際の書き方マナー、
そしてすぐに使える例文をたっぷりご紹介します。
短い一文の願い事はもちろん、
実際の絵馬にそのまま書ける
フルバージョン例文も多数掲載。
さらに、
絵馬を奉納する方法や
持ち帰った後の飾り方、
処分の仕方、
最新のトレンドもまとめています。
初めての七五三でも、このガイドを読めば迷わず安心。
家族の想いを丁寧に言葉にして、
特別な一日を一生の思い出に残しましょう。
七五三と絵馬の基本を知ろう
七五三とはどんな行事?
七五三は、
日本の伝統行事で、
3歳・5歳・7歳の子どもの成長を祝う節目です。
昔は、
髪を伸ばし始める「髪置き」、
袴を着る「袴着」、
帯を締める「帯解き」
といった成長の区切りを祝う儀式でした。
現代では
「子どもがここまで元気に育ってくれたことへの感謝」と
「これからの健やかな成長」
を祈る行事として定着しています。
七五三は、単なる記念撮影の日ではなく、家族が子どもの成長を祈り、感謝する重要な通過儀礼なんです。
| 年齢 | 性別 | 意味 |
|---|---|---|
| 3歳 | 男女 | 髪を伸ばし始める「髪置き」 |
| 5歳 | 男の子 | 初めて袴を着る「袴着」 |
| 7歳 | 女の子 | 帯を結び始める「帯解き」 |
絵馬の由来と七五三での意味
絵馬は、
もともと
「神様に生きた馬を奉納する」風習が
簡略化されたものです。
現在では、
木の板に馬の絵や神社ごとのデザインが描かれ、
願い事を文字にして奉納する形となっています。
七五三における絵馬は、
特に子どもの将来の幸せを祈る象徴として
扱われています。
「絵馬を書く=神様へ直に願いを届ける行為」
ともいえるので、
家族にとっても思い出深い儀式になります。
| 昔の絵馬 | 現代の絵馬 |
|---|---|
| 生きた馬を奉納 | 木の板に願いを書いて奉納 |
| 特別な神事で使用 | 誰でも気軽に奉納可能 |
| 神馬(しんめ)への信仰 | 願いを文字に込める |
七五三の絵馬の書き方ガイド
せっかくの七五三、
絵馬はただ書けばよい
というものではありません。
基本的なマナーやルールを知っておくことで、
神様にも気持ちが届きやすくなり、
家族の思い出としても
より価値あるものになります。
ここでは、
絵馬の書き方のポイントを具体的に解説します。
七五三の絵馬の書き方ガイド
絵馬を書くときのマナーと注意点
絵馬は、
神様に直接願いを届けるものです。
そのため、
書き方にいくつか基本マナーがあります。
- 筆記具は油性マーカーや筆ペンを使う(雨で消えないようにするため)
- 表には「奉納」、裏には願い事や感謝の言葉を書く
- 言葉はできるだけ前向きで丁寧な表現にする
- 他人を妬む内容やマイナスな表現は避ける
| 良い例 | 避けたい例 |
|---|---|
| 勉強をがんばれますように | テストで落ちませんように |
| 家族が仲良く暮らせますように | 他の子に負けませんように |
願い事の書き方の基本ルール
願い事は
「~ますように」といった
柔らかい表現でまとめるのが一般的です。
また、
子どもの名前を入れることで、
より具体的に祈願できます。
「叶ったら感謝する姿勢」
を一言添えるのもおすすめです。
例文:
- 「〇〇が健やかに育ちますように。成長を見守ってくださりありがとうございます。」
- 「これからも元気に笑顔で過ごせますように。家族一同」
個人情報や署名はどうする?
本来、
絵馬には名前・生年月日を書くのが伝統です。
ただし、
個人情報が気になる方は、
イニシャルや名字だけでも十分です。
最近では、
神社側もプライバシー配慮を重視しており、
「イニシャル推奨」とするところもあります。
| 署名の例 | 書き方 |
|---|---|
| フルネーム | 山田 太郎(2019年5月5日生) |
| 簡略版 | Y・T(2019年5月生) |
| 家族連名 | 山田家一同 |
日付は必ず記入しましょう。
いつの七五三で奉納したのか記録にもなり、
後々振り返るときに
大切な思い出になります。
七五三絵馬の例文集【シーン別】
子どもの成長を願う例文
もっとも定番で人気のある願い事です。
健やかな成長と元気な日々を祈る内容が多く見られます。
「〇〇が毎日元気に笑顔で過ごせますように」
「すくすくと健やかに成長しますように」
「けがをせず、元気に大きくなりますように」
◆フルバージョン例
「奉納 〇〇(子どもの名前)が七五三を迎えることができたことに感謝します。これからも健やかに成長し、明るく元気に日々を過ごせますように。令和7年11月15日 山田家一同」
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 名前を入れる | 誰のための願いか明確になる |
| 感謝の言葉 | 願いだけでなく、叶っている現実へのお礼を添える |
| 日付・署名 | 記念として残りやすい |
将来の夢や進学に関する例文
子どもの夢や学業に関する願い事もよく書かれます。
進学・受験を意識したフレーズも人気です。
- 「勉強に励み、元気に学校生活を送れますように」
- 「〇〇小学校に合格できますように」
- 「将来の夢に向かって努力できますように」
◆フルバージョン例
「奉納 〇〇が好きなことを見つけ、夢に向かって頑張れるように応援しています。無事に希望する学校に進学できますように。令和7年11月 父・母より」
弟妹や家族へのメッセージ例文
七五三は子ども本人だけでなく、
兄弟姉妹や家族全員への
願い事を込める機会にもなります。
- 「弟(妹)が元気に生まれてきてくれてありがとう。すくすく育ちますように」
- 「家族みんなが仲良く過ごせますように」
- 「おじいちゃんおばあちゃんも元気で長生きできますように」
◆フルバージョン例
「奉納 本日七五三を迎えられたことを感謝いたします。〇〇と弟〇〇が元気に成長し、家族みんなが幸せに暮らせますように。令和7年11月15日 山田家」
保護者から子どもへの愛情メッセージ
願いだけでなく、
子どもへのメッセージを
そのまま書くのも素敵です。
- 「七五三おめでとう。これからも笑顔いっぱいに過ごそうね」
- 「〇〇、ここまで元気に育ってくれてありがとう。これからもずっと見守っているよ」
- 「家族の宝物である〇〇が、幸せな人生を歩めますように」
◆フルバージョン例:
「奉納 〇〇へ。七五三おめでとう。3歳のころからあっという間に大きくなりましたね。これからも元気で、友だちをたくさん作って、楽しい思い出を増やしていってください。父と母より愛を込めて」
よくある質問Q&A」
七五三で絵馬を書くとき、
実際にやってみると
「これって大丈夫?」と
疑問に思うことも多いですよね。
ここでは、
保護者の方からよく聞かれる質問に答えていきます。
願い事は複数書いても大丈夫?
はい、
大丈夫です。
1枚の絵馬に
複数の願い事を書いても問題はありません。
ただし、
あまりにも多すぎると焦点がぼやけてしまうので
3つ以内に絞るのがおすすめです。
| OKな例 | 少し多すぎる例 |
|---|---|
| 学業・家族の幸せの3つ | 10個以上のお願いを箇条書きにする |
子どもがまだ字を書けない場合は?
小さな子どもの場合、
親が代筆して問題ありません。
むしろ、
親の思いを丁寧に書いてあげることに
意味があります。
また、
子どもがなぐり書きで
名前や一文字だけ書くのも
素敵な記念になります。
- 親が代筆 → 丁寧に願いを込められる
- 子どもが一部書く → 思い出になる
絵馬を持ち帰っても良い?
基本は神社やお寺に奉納します。
ただし、
最近は記念として持ち帰る家庭も増えています。
その場合は、
神棚やリビングなど
清らかな場所に飾るとよいでしょう。
| 奉納する場合 | 持ち帰る場合 |
|---|---|
| 神社の絵馬所に掛ける | 自宅の神棚・リビングに飾る |
| 神様に直接願いを届ける | 家族の思い出・インテリアにもなる |
七五三絵馬の飾り方と処分の仕方
絵馬は書くだけでなく、
その後どう奉納するか、
また持ち帰った場合の扱い方、
処分の仕方も大切です。
ここでは、
奉納から飾り方、
返納の流れまでをまとめました。
奉納のタイミングと正しい方法
七五三の絵馬は、
参拝やご祈祷の後に神社内の
「絵馬掛け所」に掛けるのが基本です。
特別な儀式は必要ありませんが、
願いを込めながら
静かに掛けるとよいとされています。
「お願いを神様に託す瞬間」だと思って、
気持ちを込めましょう。
| 奉納の流れ | ポイント |
|---|---|
| 参拝や祈祷を受ける | まず神様に感謝を伝える |
| 絵馬に願いを書く | 落ち着いた気持ちで書く |
| 絵馬掛けに奉納 | 願いが届くイメージで丁寧に掛ける |
持ち帰った場合の飾り方
絵馬を持ち帰る場合は、
家の清らかな場所に飾ります。
もっとも多いのは神棚ですが、
リビングや子ども部屋など、
家族の目に入る場所に置くのもおすすめです。
ただし、
埃がたまったり乱雑に置いたりすると
失礼になるので、
常に清潔に保ちましょう。
- 神棚やリビングに立てかける
- 写真立てのように額に入れて飾る
- 飾る場所は常に掃除して清浄に保つ
処分・返納のマナー
一定期間飾った後は、
神社やお寺に返納するのが基本です。
タイミングは
翌年の七五三や正月などの節目が多いです。
また、
「破魔矢」「御守り」「祈祷札」
と一緒にまとめて返納するケースもあります。
| 処分の方法 | ポイント |
|---|---|
| 神社に返納 | 納札所に納めるのが一般的 |
| お焚き上げ | 正月や節分の行事で行われることが多い |
| 自宅で処分 | 難しい場合は紙に包み、感謝を込めて処分する |
大切なのは「感謝を込めて手放すこと」です。
最新トレンドと活用アイデア
七五三の絵馬は昔ながらの風習ですが、
現代ならではの楽しみ方や表現方法も増えてきました。
ここでは、最新トレンドや、
家族の思い出として活用できるアイデアを
ご紹介します。
最近人気の願い事や表現
昔は
「無事な成長」といった願いが多かったですが、
最近では
より個性的で多様なメッセージが増えています。
たとえば
「夢に向かって努力できますように」
「友だちをたくさん作れますように」など、
子どもの未来に寄り添う内容が人気です。
| 従来の願い | 最近の願い |
|---|---|
| 学業成就 | 人間関係・性格形成 |
| 家族の安泰 | 親から子へのメッセージ性 |
SNSや写真で思い出を共有する方法
近年は、
絵馬をただ奉納するだけでなく
写真に残してSNSで共有する家庭も
増えています。
特にインスタグラムや
家族アルバムアプリでは
「絵馬ショット」が人気で、
子どもと絵馬を並べて撮影するケースが多いです。
- 子どもが自分で書いた絵馬を持って記念撮影
- 奉納前に家族みんなで絵馬を掲げて撮る
- 数年分の七五三絵馬を並べて成長記録にする
◆活用アイデア
「奉納した後に同じ内容をノートやスマホに残しておくと、数年後に見返して子どもの成長を実感できる」
絵馬は“未来のタイムカプセル”
のような役割も果たしてくれます。
まとめ!七五三絵馬で家族の絆を深めよう
七五三の絵馬は、
子どもの健やかな成長を祈るだけでなく、
家族の思いを言葉にして
残せる大切な習慣です。
書き方に厳密なルールはありませんが、
基本マナーを押さえつつ、
感謝と前向きな願いを込めることが大切です。
この記事では、
七五三の絵馬について以下のポイントを
解説しました。
- 七五三は子どもの成長を祝い、神様に感謝する伝統行事
- 絵馬は願いを神様に伝える大切なアイテム
- 願い事は「~ますように」と前向きに書くのが基本
- 名前・日付を添えると記念として残りやすい
- 奉納・持ち帰り・返納の方法は自由度が高い
- 最近はSNSや写真で思い出を共有する家庭も増えている
七五三の絵馬は、ただの願い事ではなく「家族の絆を深める時間」です。

ぜひ、お子さまへの思いを丁寧に言葉にして、特別な一日をさらにかけがえのない思い出にしてください
。

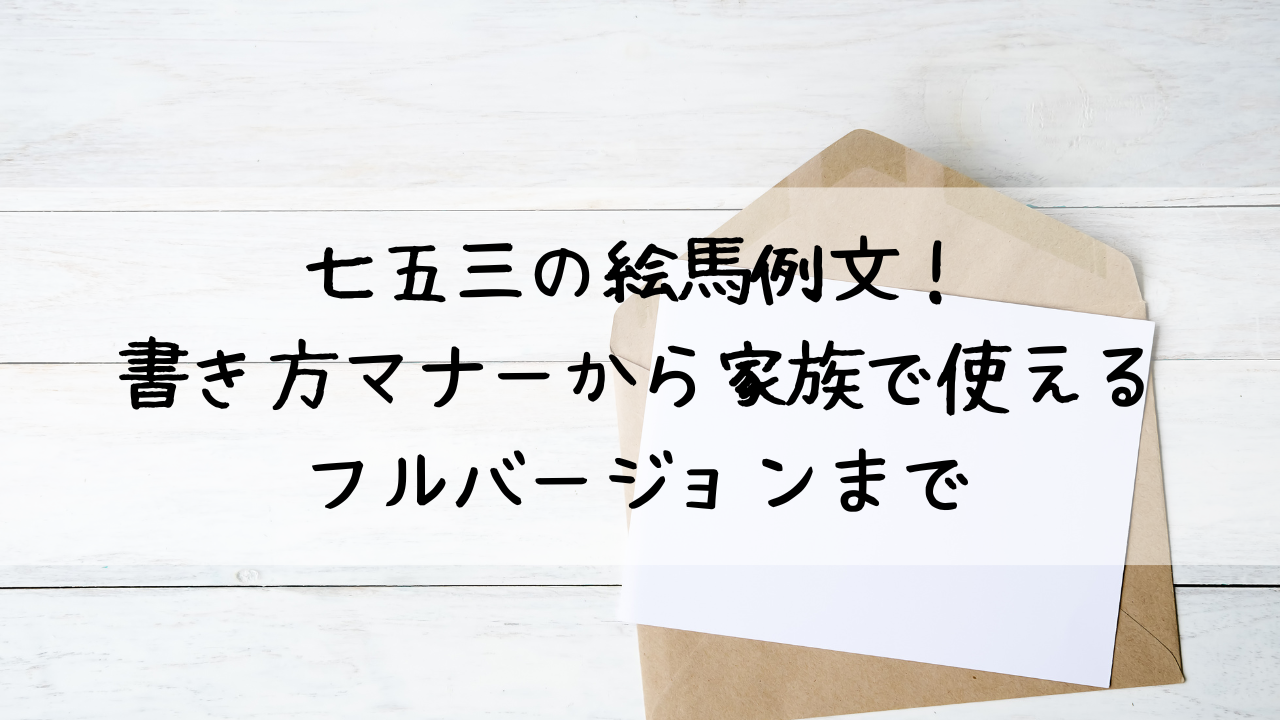
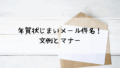
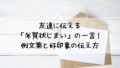
コメント