
七五三は、子どもの健やかな成長を祝う日本の伝統行事です。
しかし当日を迎えると
「神社で何を言えばいいの?」
「会食の挨拶はどうすればいい?」
と迷う方も少なくありません。
そこで本記事では、
七五三で役立つ挨拶の例文を
シーンごとにわかりやすく紹介します。
短く簡単に済ませたいときに使えるフレーズから、
しっかりと感謝を伝えられる
フルバージョンの挨拶文まで網羅。
さらに、
言葉選びや子どもと一緒に挨拶する工夫など、
マナーのポイントもまとめました。
この記事を読めば、七五三の挨拶で迷うことなく、自分らしい感謝の言葉を自然に伝えられるようになります。
親として安心して当日を迎え、
子どもと一緒に心温まる思い出を残しましょう。
七五三の挨拶が大切にされる理由
まずは
「そもそも、なぜ七五三で挨拶が重視されるのか?」
というポイントから整理しましょう。
単なる儀式だから…と思われがちですが、
実は挨拶には深い意味があります。
子どもの成長を分かち合う意味
七五三は、
親子だけのイベントではありません。
祖父母や親戚、
そして地域社会の中で
「無事にここまで育ちました」
と報告する節目でもあるのです。
そのため、
挨拶は「支えてくれた人への感謝」を
言葉にする大切な機会になります。
七五三の挨拶=子どもの成長をみんなで共有するメッセージ
と捉えるとわかりやすいですね。
感謝の言葉が人間関係を和やかにする
七五三には、
神社の神職や巫女さん、
写真館や美容室のスタッフなど、
多くの人が関わります。
そこで丁寧に挨拶をすることで、
場の雰囲気が一気に和らぎます。
「今日はありがとうございました」
の一言があるかないかで、
その後の空気が全然違うのです。
言葉の選び方以上に、笑顔や気持ちを込めて伝えることが一番大切といえるでしょう。
こうして対象ごとに整理してみると、
挨拶の本質が「感謝」であることが
よくわかります。
七五三で挨拶が必要になる場面
七五三では、
意外といろいろな場面で
「ちょっとした挨拶」が必要になります。
ここでは、
代表的なシーンを整理してみましょう。
神社参拝での挨拶
祈祷をお願いするとき、
神職や巫女さんに対して
一言添えると丁寧です。
「本日はよろしくお願いします」
と言うだけでも、
印象は大きく変わります。
神様に祈りを捧げる前に、人への感謝を表すのがマナー
と考えると自然ですね。
写真館や美容室での挨拶
着付けやヘアセット、
撮影をしてくれるスタッフにも
挨拶は欠かせません。
「丁寧に仕上げていただきありがとうございます」
と一言伝えるだけで、
気持ちよくやり取りができます。
当日の雰囲気を明るくするのは親の一言次第
といっても過言ではありません。
祖父母・親族への挨拶
七五三は親族が集まる貴重な機会です。
祖父母には
「ここまで成長できたのは皆さんのおかげです」
と感謝を伝えることが大切です。
また、
親戚には
「これからもよろしくお願いします」
と未来につながる言葉を添えると良いでしょう。
会食や食事会での挨拶
親族で集まって食事をする場合、
最初と最後の挨拶は親の役割です。
冒頭は
「今日はお集まりいただきありがとうございます」、
締めは
「これからも温かく見守ってください」で十分です。
短いけれど気持ちが伝わる言葉を心がけましょう。
シーン別 七五三の挨拶例文集(短文・フルバージョン付き)
ここからは、
実際にそのまま使える挨拶文を
シーンごとに紹介します。
短文でサッと済ませたいとき、
しっかり話したいとき、
両方のパターンを用意しました。
神社での挨拶例文
短文
「本日はよろしくお願いいたします。」
「祈祷いただき、ありがとうございました。」
フルバージョン
「本日は七五三の祈祷をしていただき、誠にありがとうございます。
おかげさまで子どもも元気に育っております。
今後とも健やかに成長できるよう見守っていただければ幸いです。」
親族への挨拶例文
短文
「本日はありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。」
フルバージョン
「本日はお忙しい中、七五三のお祝いにお集まりいただきありがとうございます。
子どもが無事に成長できましたのは、皆さまのおかげです。
これからも温かく見守っていただければ幸いです。」
会食冒頭の挨拶例文
短文
「本日はお集まりいただきありがとうございます。」
フルバージョン
「本日は○○の七五三のお祝いにお集まりいただきありがとうございます。
皆さまにお祝いしていただきながら、この日を迎えられたことを大変嬉しく思います。
ささやかではございますが、お食事をご用意しましたので、どうぞごゆっくりお楽しみください。」
会食の締め挨拶例文
短文
「本日はありがとうございました。」
フルバージョン
「本日は遠方からもお越しいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで子どもの七五三を無事に祝うことができました。
これからも子どもの成長を温かく見守っていただければ幸いです。
どうぞ皆さまもお体に気をつけてお過ごしください。」
祖父母・親戚向けの心温まる例文
「おじいちゃん、おばあちゃん、今日は来てくださってありがとうございます。
いつも○○を可愛がってくださり、とても感謝しています。
これからも元気に成長できるよう、見守ってください。」
友人や知人に伝えるカジュアルな挨拶例文
「今日は○○の七五三に来てくれてありがとう。
普段から仲良くしてもらっているので、こうしてお祝いしてもらえるのが本当に嬉しいです。
これからもよろしくね。」
職場へのお礼メール・メッセージ例文
「このたびは子どもの七五三に際し、お心遣いをいただき誠にありがとうございました。
おかげさまで子どもも健やかに成長しております。
今後とも変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。」
七五三の挨拶で気をつけたいマナー
どんなに良い言葉を選んでも、
マナーを欠いてしまうと
台無しになってしまいます。
ここでは、
挨拶のときに意識しておきたい
基本的なマナーを確認しましょう。
笑顔と姿勢を大切にする
挨拶は言葉だけでなく、
表情や姿勢からも気持ちが伝わります。
特に子どものお祝いの場では、
にこやかな笑顔が何よりの礼儀です。
「言葉7割+表情3割」くらいの気持ちで臨むと自然に良い雰囲気になります。
形式よりも心を込めた言葉を選ぶ
「立派なスピーチをしなければ」
と思う必要はありません。
むしろ背伸びした言葉より、
普段の自分らしい一言の方が
伝わりやすいものです。
大切なのは、感謝・喜び・願いの3つをきちんと盛り込むことです。
子どもも一緒に挨拶すると喜ばれる
子ども自身が
「ありがとうございました」
と一言言うだけで、
会場全体がほっこりします。
照れて小さな声になっても問題ありません。
むしろその姿が思い出になり、
親族も嬉しく感じてくれるでしょう。
親子で一緒に感謝を伝えることが、
七五三ならではの醍醐味です。
| マナーのポイント | 意識したいこと |
|---|---|
| 笑顔と姿勢 | 背筋を伸ばし、柔らかい表情で話す |
| 言葉選び | 堅苦しいよりも、自分らしい自然な言葉で |
| 子どもの参加 | 一言でも子どもに話させると喜ばれる |
よくある挨拶の悩みとその解決法
「どう挨拶したらいいかわからない」
「緊張してしまいそう」など、
七五三の挨拶には悩みがつきものです。
ここでは、
よくある悩みとその解決のコツを紹介します。
短くシンプルにまとめたいとき
長いスピーチは不要です。
むしろ
「今日はありがとうございます」
「これからもよろしくお願いします」
と2〜3文で十分伝わります。
短くても“感謝+今後”を盛り込めば完璧です。
緊張してしまうときの対策
人前で話すのに慣れていないと、
どうしても緊張しますよね。
そんなときは、
あらかじめメモを用意しておきましょう。
メモを見ながらでも構いませんし、
事前に声に出して練習しておくと安心です。
「紙を持って読む=失礼」ではありません。
むしろ誠実に準備してきた印象を与えられます。
服装や雰囲気に合わせた挨拶の工夫
正装だからといって、
必要以上に堅苦しい言葉を選ぶ必要はありません。
場の雰囲気に合わせて
「今日は来てくださって嬉しいです」
とカジュアルにしても大丈夫です。
「気持ちが伝わるかどうか」
を基準に考えるのが一番です。
| 悩み | おすすめ解決法 |
|---|---|
| 長くなりすぎるのが心配 | 2〜3文にまとめる。「感謝+今後」のセットでOK |
| 緊張してうまく話せない | メモを持ち、事前に声に出して練習 |
| 服装や場の雰囲気に迷う | 正装でも自然体の言葉で。カジュアルにまとめても問題なし |
七五三の挨拶を子どもと一緒に考える楽しみ方
七五三の挨拶は、
親がするものと思われがちですが、
子どもと一緒に考えると
ぐっと特別な時間になります。
ここでは、
親子で楽しみながら
挨拶を準備する方法を紹介します。
子どもに「ありがとう」を練習させるコツ
子どもにとっても、
挨拶は大切な学びの場です。
「今日は来てくれてありがとう」
「おじいちゃん、おばあちゃんありがとう」
といった一言を練習しておきましょう。
短いフレーズでも子どもが言うと一気に場が和みます。
照れくさそうに話す姿が、
親族にとって
忘れられない思い出になるはずです。
親子で作る七五三の思い出
挨拶を一緒に考えることは、
親子の共同作業になります。
「一緒にありがとうを言おうね」
と声をかけるだけで、
子どもは嬉しく感じます。
将来
「七五三で一緒に練習したよね」
と思い出話になることもあるでしょう。
挨拶そのものが親子の思い出づくりになる
という視点を持つと、
楽しんで取り組めます。
| 工夫 | 効果 |
|---|---|
| 短い「ありがとう」を練習 | 子どもでも無理なく言える。場が和む |
| 親子で一緒に挨拶 | 親子の共同作業になり、思い出が深まる |
| 挨拶を遊び感覚で練習 | 子どもが楽しく学べる。自然に身につく |
まとめ!七五三の挨拶で一番大切なのは「感謝」
七五三の挨拶は、
難しいスピーチではありません。
むしろ大切なのは、
子どもの成長を一緒に喜び、
支えてくれる人たちへ素直に感謝を伝えることです。
短い一言でも、
丁寧に話せば十分に気持ちは伝わります。
長文よりも心のこもった一言の方が印象に残るものです。
また、
子ども自身にも
「ありがとう」と言わせることで、
親子にとって忘れられない思い出になります。
挨拶は形式ではなく、気持ちを伝えるためのツールと考えると、
肩の力が抜けて自然に話せるでしょう。
この記事で紹介した例文やマナーを参考に、
自分らしい挨拶を用意してみてください。
当日はきっと、
子どもも親も、
心温まるひとときを過ごせるはずです。
| ポイント | チェックリスト |
|---|---|
| 感謝 | 「支えてくれた人にありがとうを伝えたか?」 |
| シンプルさ | 短くても気持ちがこもっているか? |
| 親子の共同 | 子どもと一緒に挨拶する工夫をしたか? |

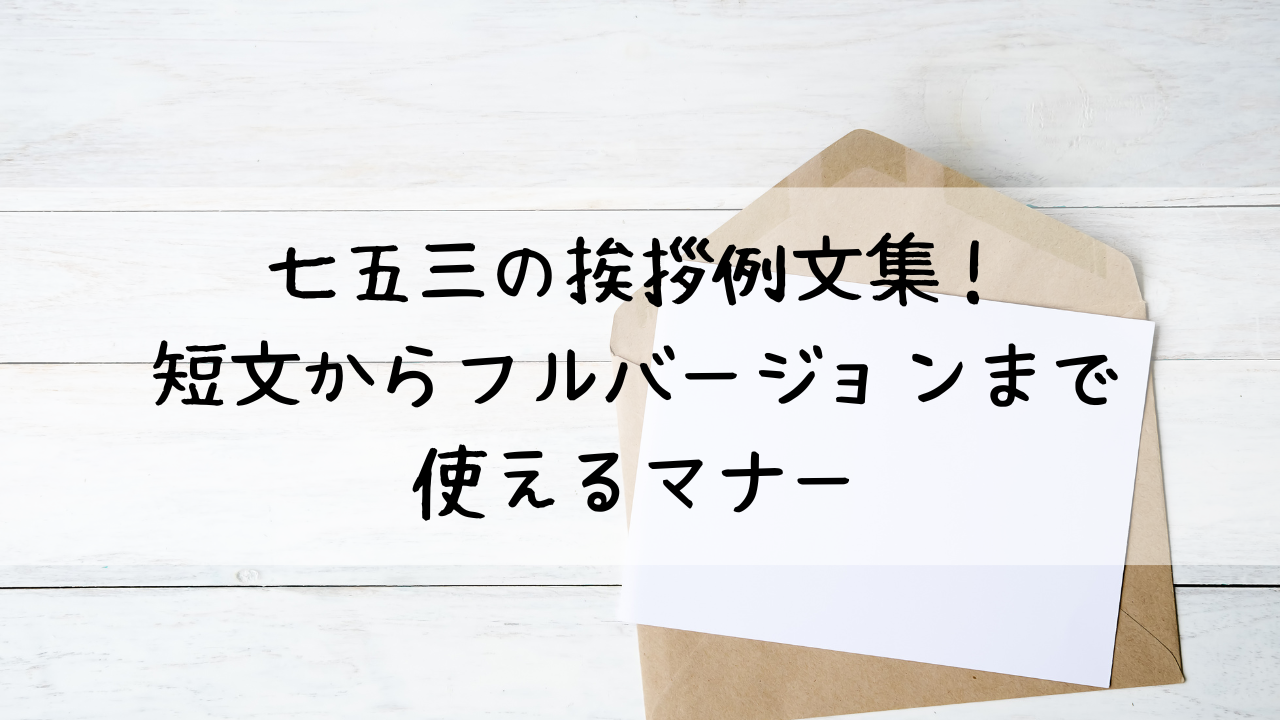
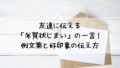
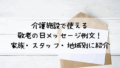
コメント